2016年度(平成28年度)大学収容力指数|都道府県ランキング
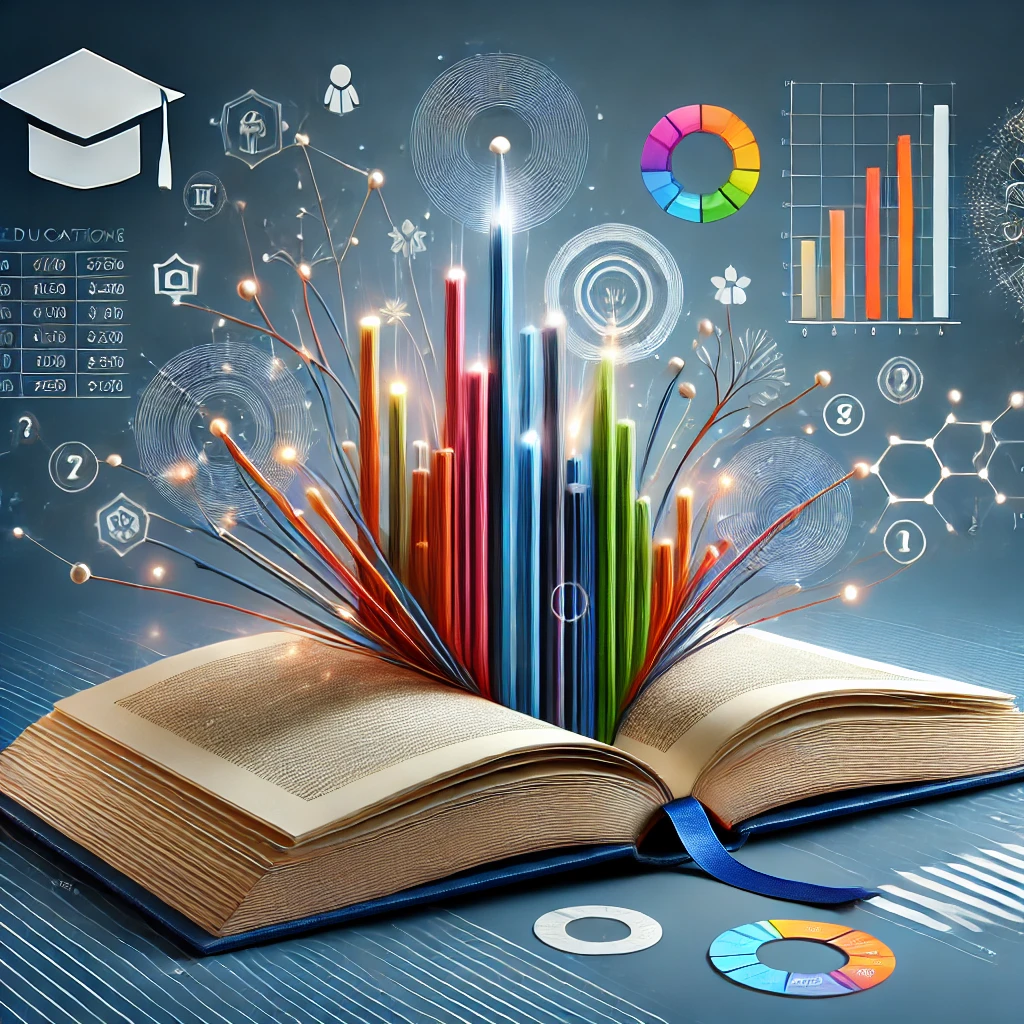
2016年度(平成28年度)の大学収容力指数データが発表されました。この指数は、高校卒業生の中でどれだけの割合の生徒が地元の大学に進学できるかを示しており、都道府県別に大きな違いが見られます。この記事では、大学収容力指数が高い都道府県から低い都道府県まで、ランキング形式で詳しく見ていきます。
もくじ
ランキング基準の説明
ランキングは、高校卒業生に対する大学の収容力を示す指数に基づいています。この指数は、地域内の大学がどれだけの高校生を受け入れられるかを示しており、大学の数や進学希望者の数が大きく影響しています。
2016年度(平成28年度)都道府県別大学収容力指数(高卒者のうち大学進学者数)ランキング:
| ランキング | 都道府県名 | 収容力指数(-) |
|---|---|---|
| – | 全国 | 118.6 |
| 1 | 京都府 | 241.3 |
| 2 | 東京都 | 233.6 |
| 3 | 大阪府 | 131.9 |
| 4 | 宮城県 | 130.6 |
| 5 | 福岡県 | 130.5 |
| 6 | 神奈川県 | 129.5 |
| 7 | 石川県 | 123.7 |
| 8 | 愛知県 | 123.2 |
| 9 | 滋賀県 | 118.3 |
| 10 | 北海道 | 115.8 |
| 11 | 岡山県 | 115.7 |
| 12 | 兵庫県 | 107.2 |
| 13 | 山口県 | 106.2 |
| 14 | 埼玉県 | 103.4 |
| 15 | 千葉県 | 102.9 |
| 16 | 広島県 | 101.2 |
| 17 | 山梨県 | 98.4 |
| 18 | 徳島県 | 96.5 |
| 19 | 熊本県 | 94.1 |
| 20 | 鳥取県 | 91.0 |
| 21 | 沖縄県 | 86.0 |
| 22 | 高知県 | 84.9 |
| 23 | 大分県 | 80.1 |
| 24 | 長崎県 | 79.1 |
| 25 | 群馬県 | 78.9 |
| 26 | 鹿児島県 | 77.7 |
| 27 | 奈良県 | 77.2 |
| 28 | 新潟県 | 73.7 |
| 29 | 青森県 | 73.1 |
| 30 | 山形県 | 73.1 |
| 31 | 福井県 | 65.9 |
| 32 | 愛媛県 | 65.6 |
| 33 | 島根県 | 64.7 |
| 34 | 秋田県 | 63.9 |
| 35 | 宮崎県 | 61.3 |
| 36 | 茨城県 | 61.1 |
| 37 | 富山県 | 59.4 |
| 38 | 岩手県 | 57.6 |
| 39 | 佐賀県 | 57.2 |
| 40 | 香川県 | 55.2 |
| 41 | 岐阜県 | 54.0 |
| 42 | 栃木県 | 53.6 |
| 43 | 静岡県 | 51.5 |
| 44 | 福島県 | 47.5 |
| 45 | 長野県 | 46.2 |
| 46 | 三重県 | 44.4 |
| 47 | 和歌山県 | 43.1 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
| 都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
| 同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
| 同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
| 同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
| 同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
上位5都道府県の詳細
- 京都府(241.3)
京都府は大学の収容力指数が最も高く、全国平均を大きく上回っています。京都は日本の学問の中心地として知られ、京都大学や同志社大学など、全国から学生が集まる大学が多数あります。そのため、地域内の高校生にとっても豊富な進学先が存在しています。 - 東京都(233.6)
東京都は、日本の首都であり、多くの大学が集中しています。東京大学をはじめ、早稲田大学や慶應義塾大学など全国有数の大学が存在し、都内の高校生にとって進学先が豊富です。 - 大阪府(131.9)
大阪府も関西の中心地として、多くの大学があります。大阪大学や関西大学などがあり、地元の高校生が進学しやすい環境が整っています。 - 宮城県(130.6)
宮城県は東北地方の中心として、東北大学をはじめとする多くの大学が集中しています。東北地方全域から学生が集まることもあり、大学の収容力が高いです。 - 福岡県(130.5)
福岡県は九州地方の中心地であり、九州大学をはじめ、複数の大学が存在します。九州全域からの学生が集まる一方で、地元の高校生も豊富な進学先があるため、収容力が高くなっています。
中間層の動向
全国平均の118.6に近い数値を示す都道府県には、滋賀県(118.3)や北海道(115.8)、**岡山県(115.7)**などがあります。これらの県は、地域内に複数の大学が存在し、進学先がある程度充実していることがわかります。
収容力が低い都道府県
一方、収容力指数が低い都道府県も多く存在します。最下位の**和歌山県(43.1)**は、大学数が少なく、進学希望者が他県の大学へ進むケースが多いと考えられます。同様に、**三重県(44.4)や長野県(46.2)**も収容力が低い県としてランクインしています。
カテゴリ別ランキングの考察
- 都市部 vs 地方
都市部では大学が多数集中しているため、大学収容力が非常に高い傾向があります。これに対して、地方では大学の数が限られており、地元での進学が難しいことが収容力の低さにつながっています。 - 進学先の選択肢
地方では大学数が少ないため、多くの高校生が他県に進学する傾向にあります。一方で、都市部では進学先が豊富であり、地元での進学が容易です。
まとめと将来の展望
2016年度の大学収容力指数を基にすると、都市部には進学先が豊富であり、地方では進学先が限られていることがわかります。今後は、地方においても大学の充実を図り、地元での進学機会を増やす取り組みが重要となるでしょう。
その他統計情報はコチラから‼︎




